「アーユルヴェーダ」と聞くと、どこか特別な人が取り入れる東洋の伝統医学、というイメージを抱いていた私。しかし、この『現代に生きるアーユルヴェーダ』を読んで、アーユルヴェーダは決して特別なものではなく、むしろ現代社会に生きる私たちにこそ必要な“生き方のヒント”なのだと強く感じました。
本書は、インド5000年の叡智とも言われるアーユルヴェーダを、現代の生活に無理なく取り入れられるように、わかりやすく、そしてとても丁寧に紹介してくれています。単なる健康法や食事法のガイドではありません。もっと深いところにある、「自分を知ること」「自然と調和すること」「本来のリズムに戻ること」──この3つが、どれだけ私たちの心と体を楽にしてくれるかを、本書は静かに教えてくれました。
特に印象的だったのは、「ドーシャ(体質)」という考え方です。ヴァータ、ピッタ、カパという3つのエネルギーが人それぞれの性質を形づくっているという考え方は、占いや性格診断とはまったく違う深さがあります。自分のドーシャを知ることで、「なぜ自分はこう感じるのか」「なぜ無理がきかないのか」といった疑問が腑に落ちていきます。
私自身は、ピッタ体質の傾向が強く、頭で考えすぎてしまったり、完璧主義になったりすることがよくあります。本書を通じて、それが体質的に自然なことであり、無理に変えようとするのではなく「整える」ことが大事だと知り、なんだか肩の力が抜けたような感覚になりました。
また、アーユルヴェーダの基本にあるのは「自然とともに生きる」という価値観です。朝は日の出とともに起き、夜は早めに休む。食事は旬のものをよく噛んで味わう。体に溜まった毒(アーマ)を溜めすぎないよう、日々の生活の中で少しずつ整えていく──どれも昔ながらの当たり前のようでいて、現代では見失われがちな知恵ばかりです。
アーユルヴェーダに触れることで、私たちは“便利さ”の代わりに何か大切なものを手放してきたのかもしれない、という気づきもありました。例えば、冷たい飲み物を年中飲み、夜遅くまでスマートフォンを手放せず、食事を「栄養素」としてしか見ない…。そうした日常が、心や体にどれほどの負荷をかけていたのかを、本書を読んで改めて実感しました。
本書では、難しい専門用語や医学的な説明よりも、「暮らしの中でどう生かすか」に重きが置かれています。例えば、簡単なマッサージの方法や、体質に合わせた食材の選び方、季節ごとのセルフケアの知恵など、すぐに取り入れられる内容が豊富に紹介されています。その一つひとつが、どこか懐かしく、そしてとてもやさしいのです。
著者の語り口も穏やかで、「こうしなければいけません」という押しつけがましさは一切ありません。むしろ、「自分に合ったリズムを見つけていきましょう」というスタンスで、読者をそっと導いてくれます。だからこそ、読み終えたあとに「よし、明日から生活をガラッと変えよう!」という気負いではなく、「今日の夕飯、ちょっと温かいスープにしてみようかな」というような、静かで前向きな気持ちになれるのです。
そして何より、この本が伝えてくれているのは「自分を大切にすること」。ただの健康管理ではなく、心身を通じて“本来の自分”に戻るための知恵が、ここには詰まっています。忙しく、常に何かに追われるような現代の暮らしの中で、アーユルヴェーダという知恵は、まるで“深呼吸するような時間”をもたらしてくれる存在なのだと感じました。
アーユルヴェーダに少しでも興味がある方はもちろん、「最近なんとなく不調が続く」「心が疲れている気がする」という方にも、本書は静かなヒントを与えてくれるはずです。そして何より、「もっと自分を知りたい」と思っているすべての方に読んでいただきたい一冊でした。
『現代に生きるアーユルヴェーダ』(ヴァサント・ラッド 著)
▶ Amazon(招福堂ネットショップ)で詳細を見る

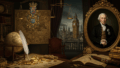
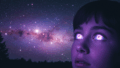
コメント